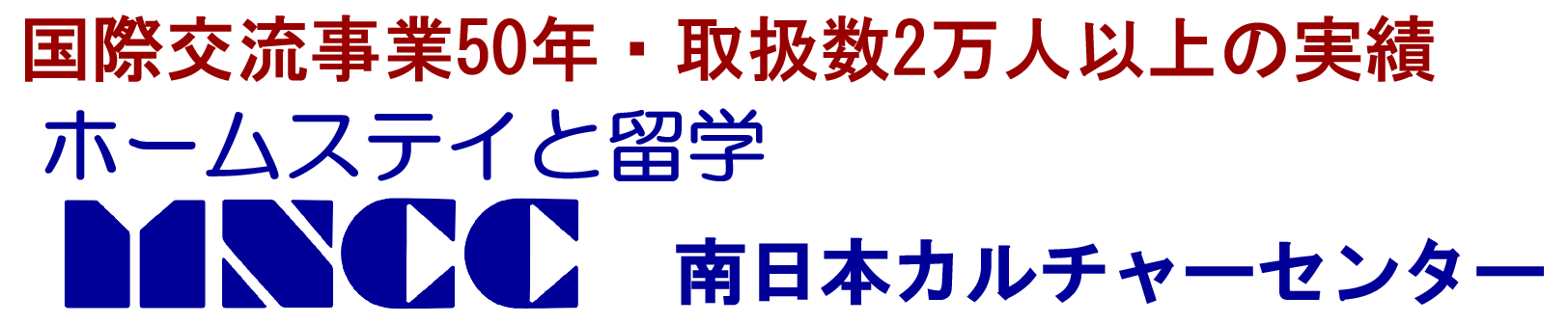
HOME > ホームステイの現状と提言 - 1 変わりゆくホームステイ
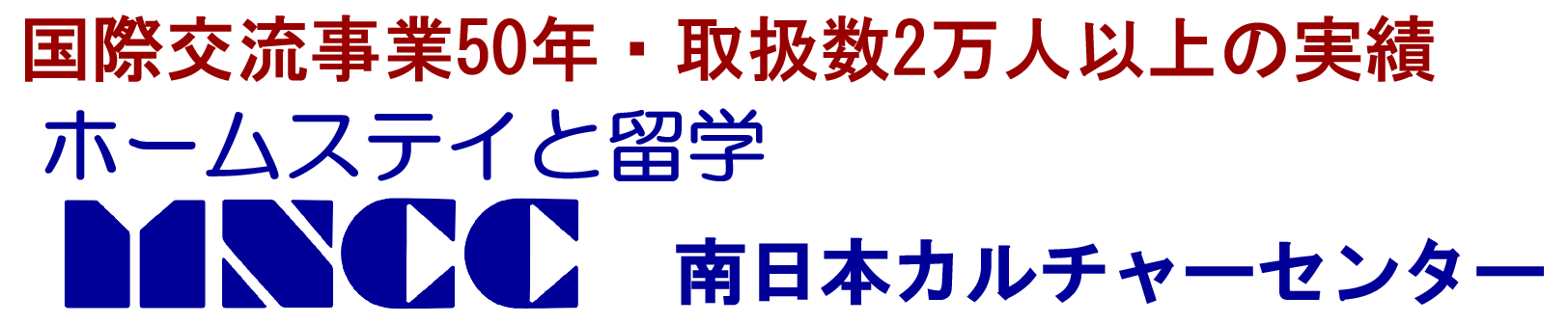
|
ホームステイとは何なのか。ホームステイでは何が得られるのか。40年以上にわたって、国際交流教育事業に関わってきた南日本カルチャーセンターによるホームステイの現状と提言です。
HOME > ホームステイの現状と提言 - 1 変わりゆくホームステイ |
|
執筆者: 南日本カルチャーセンター 代表取締役社長 濱 田 純 逸 ■ 1 変わりゆくホームステイ1974年(昭和49年)7月、九州で初めて、ホームステイの参加者達が西鹿児島駅からアメリカへ出発する時、参加者も保護者も抱き合って、人目をはばかることなく涙を流しながら別れたことが、まるで昨日のように思い出されます。そして、約十年間は、全く同じような出発光景を、九州各県のいたるところで見ることができました。でも、それから約四十年、昨年の出発時に、涙を流しながら別れる生徒と保護者は、どこにも見当たりません。そうなってから、同じく十年ぐらいはなるでしょう。親子が涙ながらに別れていたのが、なぜ笑顔で別れるようになったのでしょうか。この変遷の中に、日本のホームステイの問題性が、凝縮しているといっても過言ではありません。 今となっては信じられない話かも知れませんが、40年前の涙は、アメリカに行く生徒も、送り出す親も、未知の世界を目の前にした不安と恐怖の涙だったのです。「ホームステイ」という言葉すら市民権のない時代ですから、英語も分からない子ども達が、一ヶ月間もアメリカ人の他人の家庭で、無事に過ごして帰ってこられるだろうかと言う恐ろしさは、参加者や保護者にとって想像以上のものでした。周囲にホームステイ体験者は一人としていない、ましてや、初めて海外に出るという生徒と、自分自身ですら行ったこともない、そんな親ばかりですから、その分だけみんな真剣に国際理解教育としての「ホームステイ」に取り組んだものです。事前の英語学習や自文化学習でも、現地の異文化学習でも、ホームステイ参加者には、誠実で、真摯な相互理解の学習姿勢がありました。 例えば、アメリカ生活第二日目、ホームステイ地の市長室に表敬訪問に行った際、その町の行政について英語で説明する担当者の話を、参加者達は当然ながらほとんど理解できないにもかかわらず、全員がノートを片手に、鉛筆で一生懸命にメモや記録を取ろうとするその姿が象徴的なものでした。それが現在においては、説明する広報官の英語をかたわらに、市長の椅子に勝手に座り、はしゃぎながら右手はピースのサインを突き出して、デジタルカメラのシャッターボタンを押し合うという、そんな光景が時々散見されます。誰もがホームステイという言葉を使うようになり、その参加者や留学体験者が周りに溢れるようになって、ホームステイは気軽に参加できるようになりました。何しろ、アメリカに渡航するのに、150名を超える団体が、当時の国鉄の鹿児島本線上りの始発駅である西鹿児島駅に夕方集合し、全員が寝台列車に乗って岡山駅まで行き、翌朝に新幹線に乗り換えて、羽田空港から国際線に搭乗するという行程ですら、今考えれば信じられないような話しです。でも、その時代の価値と背景をこの行程からも、窺い知ることが出来るように思います。それだけ、アメリカは遠い国でしたし、海外渡航に覚悟が必要だった時代です。それから40年も過ぎ去ったのですから、時代は変わり、日本社会が「国際化」「自由化」のイデオロギーのもとに、国際交流の輪もそれなりに自由に広がっていったのかもしれませんし、それ自体は決して悪いことだとは思いません。いたずらに不安になるのではなく、いい意味での気軽さは必要だと思います。でもその気軽さが、安易さに変化していくことが危険であり、間違いなのです。 私は40年の歳月の間、一年たりとも欠くことなく、毎年、子ども達の過ごすホームステイの現場に立ち続け、直接、彼らの世話をしてきました。そして、異文化学習の場であったホームステイが、観光旅行やお買い物ツアーと化して、明らかに現在でも変容し続けている現実を、今でも見ております。そして、国際理解教育の黎明期から携わっている者として、今やホームステイとは、まるで「児童、生徒、学生のための海外旅行」に過ぎないのではないかという自問から始る危惧と不安が、片時たりとも頭から離れることはありません。「そうあってはならない」という強い信念と、「易きに流れていく」眼の前の現実との乖離は埋まることはなく、むしろ広がる一方であり、多勢に無勢、老いた敗残兵のごとく、暗澹たる気持ちになりながらも、これらの現状を分析してみたいと思います。 |
| MNCC 南日本カルチャーセンター Copyright © 2018 MinamiNihon Culture Center. All Rights Reserved. http://www.mncc.jp |