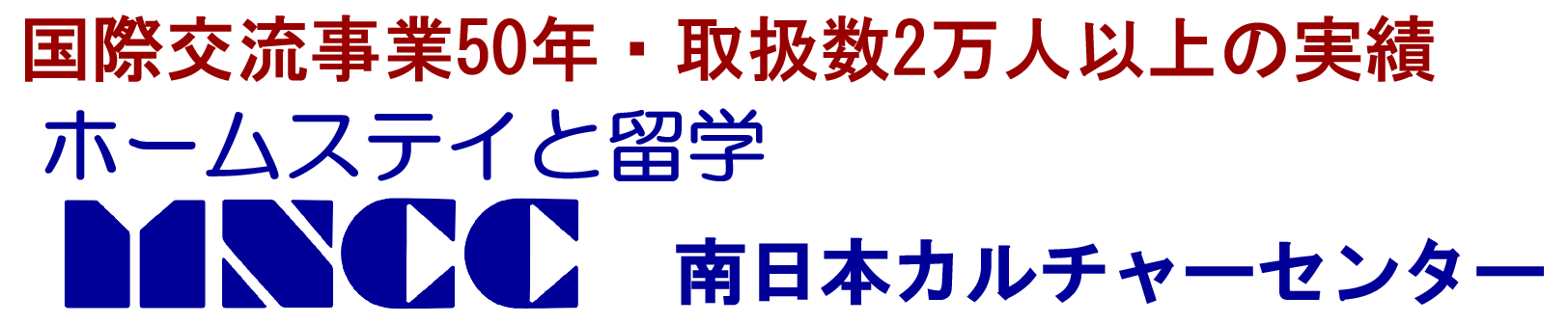
HOME > ホームステイの理念 - 1 教育の一環として
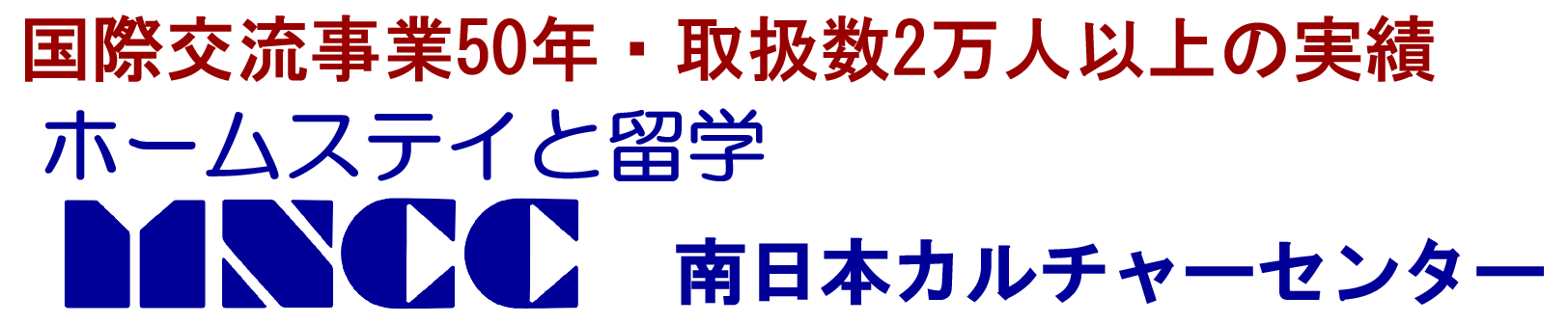
|
ホームステイとは、何のために行くのか?
HOME > ホームステイの理念 - 1 教育の一環として |
|
執筆者: 南日本カルチャーセンター 代表取締役社長 濱 田 純 逸 ■ 1 教育の一環として南日本カルチャーセンターが、九州の各県地方新聞社と共催し、各県・市教育委員会などの後援を得て、実施いたしております「アカデミック ホームステイ プログラム」も、昭和49年(1974年)に始まって以来、早いもので40年の年月が経ち、この間に1万5千人以上の子ども達が参加いたしました。既に、親子二世代に亘る参加者も百組を超え、おそらく、日本で、最も歴史の長いホームステイプログラムであり、最も参加者数の多いホームステイだろうと思われます。 プログラムの発足当初、「どのくらいの数の子どもが参加を希望するものだろうか」、「親元を離れて、中学生がひとり、アメリカで一ヶ月間生活できるものだろうか」という主催者の素朴な疑問や、「このような偏差値教育中心の世相の中で、保護者は一ヶ月間の異国での夏休みの体験をどのように考えるだろうか」、また、「学校の先生方は、このプログラムをどのように位置づけられるだろうか」という、保護者や教育者側の立場も検討されました。そんな状態の中で、今でも特筆できることは、当時の文部省から出向で、鹿児島県教育委員会に赴任されておりました山中昌裕教育長だけが、「早期参加の効用」という強い信念をもっておられたようで、私ども主催者に、「大学よりは高校、高校よりは中学」の時の参加を促進していただきたいと言う趣旨のお言葉を、事業前の企画段階でいただいたのが、唯一、積極的で、明確な意図を示した見解でした。主催者側にさえも、「果たしてこのホームステイに、どれだけの意義や成果があるのだろうか」という疑問を抱える中で、県教育長のこの見解を今考えてみれば、見事という他ないほどの先見性のある視点だと思われます。 このように国際理解教育の黎明期の時代に、ホームステイプログラムの意義と成果を模索することは、センターにとって、測り知れない程の大問題であり、回避する事のできないものでありました。でも、考えるほどに厄介で、困難なテーマであり、何もかもが未知のものでしかないという状況だったのです。といいますのが、現在でこそ、国際交流プログラムが数多く生まれ、多くの子どもたちにとって、これらは珍しいものではありませんが、40年前の時代、このようなホームステイプログラムは全国的にもほとんど皆無で、プログラムに関するデータや情報などほとんど存在しなかった訳です。大学生や高校生を対象としたものは、少しあったものの、ほとんどが個人的な語学留学や高校留学といった、英語力の向上を目的とするような内容のもので、異文化学習を目的とした国際理解プログラムは、ほぼ皆無というような状況でした。さらに、中学生を対象としたプログラムにいたっては、日本全国どこを探しても無かったわけですから、どれだけの意義や成果があるかと考えてみても、全く雲をつかむような話しで、内輪での論議も観念論に終始せざるを得ないといったような実状でした。信じられないことかもしれませんが、今では誰もが知っている「ホームステイ」という言葉すら、一般的な名詞としての認知度は極めて低く、もっぱら「民泊」という言葉を併用しながら、保護者や参加者にその内容を説明しなければならないというような有様でした。英語の先生ですらも、「ホームステイ」という言葉のイメージを、現在と同様には把握できないほど、「ホームステイ」が浸透していなかった時代のことですから、仕方のないことなのかもしれません。しかし、そのような状況の中でも、常に大命題として私共の念頭にあったものは、「人問形成の中の教育の一環として」と言う事でありました。 暗中模索の中で、第一回のプログラムがスタートいたしましたのは、昭和49年で、九州では鹿児島県内だけで募集をしました。ところが、新聞紙上の社告に掲載されて、その反響は目ざましく、最終的な参加者は157名という大変な数にのぼり、予想だにしなかったその数の大きさに驚愕すると同時に、その使命の重大さに慄然とするばかりでした。この時、日本全国からの参加者は526名、そのうち、鹿児島県だけで157名、すなわち約三割を占めていたわけです。普通、海外旅行を企画する場合、20人から30人の参加があれば大成功という事ですから、いかにこの数字か驚異的なものであったか、おわかりいただけると思います。私共が驚きましたのは、その数もさる事ながら、もう一つの注目すべき現象が内在していたということです。それは、参加者における中学生の割合でした。その内訳は、中字生、127名、高校生、17名、大学生13名であり、この中学生、127名という数字は、日本全国から参加した中学生の実に約5割近くにあたります。つまり、中学生の参加者の半数は、鹿児島県の生徒で占められていたという、不可思議な現象です。これは大変な事実でありました。いかに、明治の頃から進取の気風に富んだお国柄とはいえ、他県と比較して、県民所得の低い鹿児島県のこの現象は、明治維新当時の薩摩藩のように「教育にかける情熱の現われ」としか理解できませんでした。そして、「鉄は熱いうちにうて」の言葉通り、また、前述の教育長の言葉通り、中学生の参加を強く目論でいた私共の方針に見事、呼応して、その意を強くしたものでした。 出発当日、西鹿児島駅における結団式には、山中教育長も駆けつけられ、参加者と保護者を前に、ハンドマイクを手にして「特に、中学生という若い時にこそ、このような体験が最も貴重である」という趣旨の挨拶をされ、流石に文部省官僚の教育長として、皆がその知見の高さを感じたものでした。また、帰国後の報告会においては、当時の鹿児島県知事である金丸知事までもが出席され、一人一人の参加者の報告を丁寧にお聞きになられました。さらに、各グループの代表者は知事からの親書を、ホームステイする町の市長に届けるという「小さな外交官」としての役目を負っておりました。民間の行なう事業に、官がこれまで積極的に関わりを持つことなど、今では到底考えられないことですが、この事業に対する教育行政側の並々ならぬ熱意と協力もあり、以後、徐々に九州各県で、このプログラムは取り入れられていきました。引率していただきました先生方も、既に500名を超えており、地域的なものであったものが拡大を重ね、現在ではインターネットを通して、さらに広がりを見せております。また、このプログラムを核にして「冬のホームステイ」「わんぱく留学」「ジュニア留学」「シニアのホームステイ」「米国公立高校交換留学」などのプログラムが企画され、現在でも進化しております。そして、地方自治体が実施する「青少年海外派遣事業」「青少年人材育成事業」の一つとして業務委託を請け、助成金制度も大きな広がりを見せ、数多くの参加者がこれらの恩恵を受けております。 |
| MNCC 南日本カルチャーセンター Copyright © 2013 MinamiNihon Culture Center. All Rights Reserved. http://www.mncc.jp |